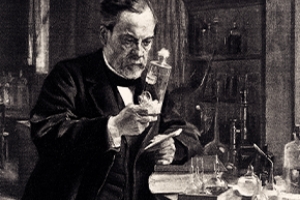「京都酵母」の誕生

~京都・伏見の日本酒シーンに加える新たな価値創造~
明治期以降の日本酒醸造における応用研究は、日本酒醸造の科学的解明と安定醸造に主眼があった。日本醸造協会が設立され、「きょうかい酵母」として優良酵母の頒布が始まったのも、その流れの上に立脚したものだった。しかしその後、日本酒を取り巻く環境は大幅に変化する。昭和48年(1973)をピークに日本酒の製造量は減少へと転じた。生活の洋風化が進み、ビールやワインなどの洋酒がより多く消費されるようになった結果だ。
昭和43年(1968)、熊本で分離された華やかな芳香を出す酵母を元株として、きょうかい9号酵母が頒布された。これを皮切りに、各地の蔵元は、年に一度の全国新酒鑑評会への出品酒を、香り高い酵母を使用した精米歩合の低い吟醸酒に切り替えていく。当初これらの出品酒は、あくまでも鑑評会用で、一般に発売されることを目的としたものではなく、知るものはわずかだった。
しかし、昭和40年代(1970年代)後半から、こうした香り高い吟醸酒を入手し「幻の酒」として飲む活動が東京で始まった。それに魅了されたメディア関係者などを中心に、昭和50年代(1980年代)以降のバブル景気の中、香り高い各地の吟醸酒を楽しむムーブメントが活発になった。これが「吟醸酒ブーム」である。この時代の流れの中で、公設試験研究機関や大学、民間企業などを中心として、より吟醸香を出す新たな酵母の開発が進み、エステル高生産性酵母、リンゴ酸高生産性酵母といった地域酵母が多数生み出されることとなる。
当時の京都市工業試験場(現京都市産技研)は、昭和30年代(1960年代~)からきょうかい6号系の「工試1号」、7号系の「工試2号」を中心に、主に京都市内の酒蔵へ分譲を行っていた。これらの酵母は、安定醸造に資するものとして、主に普通酒の製造のために利用されていた。しかし、吟醸酒のブームを目の当たりにした京都市内の酒蔵から、「香りが高い酵母を開発してほしい」との声が高まっていた。
日本醸造協会からも、平成に入ってから、吟醸用酵母としての1601号酵母、1701酵母がデビューしていた。時を同じくして京都市工業試験場でも、京都市内の酒蔵からカプロン酸エチルを高く生産し、発酵力もある酵母をいくつか選抜して育種しており、平成15年(2003)には221番とナンバリングされた香り高い新規開発酵母がすでに存在していた。これをなんとか世に出したいと、当時の筒井延男研究員が佐々木酒造に「試験醸造してもらえないだろうか」と声をかけた。この試験醸造の成功を経て、平成16年(2004)に分譲開始されたのが、のちの「京都酵母」シリーズ第1号となる京都地域限定酵母「京の琴(こと)」だった。全国的な大ヒットとなる平成18年(2006)のきょうかい1801号酵母リリースから遡ること1年前のことだった。「京の琴」は、現在も吟醸酒用酵母として京都市内の多くの酒蔵で採用されている。
酵母の出す香りのうち、重要なものは洋梨のような香りを出すカプロン酸エチルと、バナナのような香りを出す酢酸イソアミルだが、このうち、酢酸イソアミルを高く生成する酵母が、平成19年(2007)に開発された「京の華(はな)」である。「京の華」はバナナのような香りが高いだけでなく、有機酸生成量も高いので、「京の琴」とは異なるタイプの個性的な商品開発に利用されている。
日本酒の味に影響を与える成分である有機酸のうち、リンゴ酸は爽やかな酸味を呈し、一方で、コハク酸はうまみやコクに影響を与えるとされる。京都市産技研は、リンゴ酸の生成量の多い酵母とコハク酸の生成量の多い酵母をそれぞれ京都市産技研の保有株から選抜し、実用化することに成功した。平成26年(2014)、リンゴ酸生成量の多い酵母「京の咲(さく)」を冷酒に向く酵母として、平成29年(2017)、コハク酸の生成量の多い酵母「京の珀(はく)」を燗酒に向く酵母としてそれぞれ分譲を開始している。
さらに、京都市産技研では、冷酒に向く大吟醸用酵母として、香り高い既存の「京の琴」酵母からリンゴ酸を高く生産する酵母の選抜に成功した。果実様の香りと甘酸っぱい味わいがまるで「初恋」を思わせることから、この酵母は「京の恋(こい)」と名付けられ、令和2年(2020)から分譲開始となった。
ここで生まれた一つの問題意識がある。ワインは、原料ブドウの生産地や醸造所、生産法、使用品種などによって格付けされ、消費者はその格付けに基づいて品質を評価する。一方、日本酒においては、原料米の精米歩合に主眼をおいた「大吟醸」や「吟醸」という名称による一種のブランド化がなされており、消費者は「どれだけ原料米が精米されているか」をもとに日本酒の品質を評価する傾向にある。日本酒の酒蔵にとっては、「米を削れば付加価値になる」状況を呈しており、精米歩合1桁台の日本酒が登場するなど、「精米歩合」というスペックが過度に重視されてきている。それは、本当に日本酒の魅力を価値として創造しきれているのだろうか。
平成26年(2014)以降、京都市産技研では、こうした問題意識から、「酵母が作り出す多様な香りと味わい」に焦点をあてて、独自酵母についてブランディングする試みを続けている。酵母が生成する有機酸や芳香エステルの種類や割合によって、完成品である日本酒の香りや味わいは違ってくる。独自の酵母を用いて京都の酒蔵が多様な日本酒を製造することにより、消費者は、酵母が生み出す多種多様な香りと味わいによってその日呑む日本酒を選び、それぞれにあったスタイルで楽しむことができるという発想だ。精米歩合の違いによるランク付け一辺倒から脱却した新たな提案だといえよう。この発想に基づき、京都市産技研では、令和3年(2021)からこの5種類の酵母を新たに「京都酵母」としてブランド化した。
この中で特筆すべき取り組みがある。令和元年(2019)から、京都市産技研が主体となって、「アッサンブラージュ」技術を活用した製品開発を進めた。「アッサンブラージュ」とは、ワイン業界用語で、複数の原酒をブレンドすることで立体的な味わいの奥行きを生み出す技術だ。2種類の違う酵母からできた日本酒を最適な比率で「アッサンブラージュ」することで、単独の酵母使用では生み出せない複雑な香りや味わいを生み出すことができる。これを、伏見の増田德兵衞商店に依頼した。増田德兵衞商店では、原料米等が同じ条件で「京の華」と「京の恋」の日本酒を製造した。それらの成分分析と官能評価は京都市産技研が担い、それぞれの日本酒の良い部分を味わうことができるブレンド比が、「京の華」:「京の恋」=2:8の比率であることを突き止めた。この製品については、当初より、京都市産技研のデザインチームが製品のコンセプトを検討、製品のパッケージ全体のデザイン等に反映させながら、令和2年(2020)、「京の恋」単独の製品である「月の桂 The Branche」と「京の恋」と「京の華」をブレンドした製品である「月の桂 The Assemblage」をそれぞれ製品化し、好評を得た。

「京都酵母」の取り組みはまだ始まったばかりだが、すでに国内外で一定の反響を得ている。酵母が作り出すさまざまな香りと味わいによって呑み方を提案するブランディングは、従来の精米歩合のみによる日本酒の価値創造に代わるオルタナティブとして受け入れられていくだろう。酵母が描く色とりどりな未来は、すぐそこまで来ている。
(文・山口吾往子)
<参考文献>
廣岡青央、清野珠美(2021)「京都酵母による日本酒新製品開発~ランクからスタイル重視の製品開発へ」日本農芸化学会『化学と生物』Vol.59No.7p354-359
空太郎(2015)「日本酒を美味しくする「きょうかい酵母」(協会酵母)の実態に迫る<前編>」『SAKETIMES』(https://jp.sake-times.com/knowledge/word/sake_g_kyoukaikoubo_1)(最終閲覧:2022-11-9)
山口吾往子(2018)「燗にしてから本領発揮!京都市産業技術研究所が開発した”燗酒向け”の酵母「京の珀」の魅力を徹底解説」『SAKETIMES』(https://jp.sake-times.com/think/study/sake_g_kyonohaku-eikun)(最終閲覧:2022-11-9)
山口吾往子(2020)「京都産の新酵母とブレンド技術で造る新たな日本酒の味わい─増田德兵衞商店と京都市産業技術研究所のチャレンジに迫る」(https://jp.sake-times.com/knowledge/description/sake_g_kyoto-yeast)(最終閲覧:2022-11-9)
権淑敬「(あのとき・それから)1975年 吟醸酒ブームの夜明け 品質を味わい・見せる時代へ」2017年11月22日『朝日新聞デジタル』(最終閲覧:2022-11-9)
その他の歴史を読む
- #酒造りと酵母の歴史
- #京都酵母