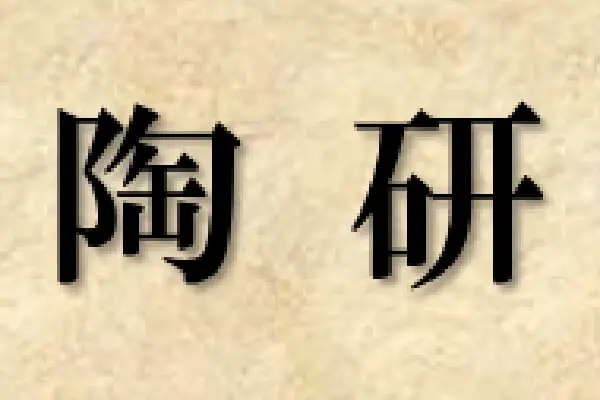技術的課題を解決するための研鑽と交流の場

研究会は、伝統産業から先進産業に至るまで、さまざまな技術分野において設立され、長い歴史の中で、現在10の研究会(約600の個人、法人などが会員)が活動されており、京都市産業技術研究所ユーザーズコミュニティ(産技研UC)に団体会員として参画いただいています。産技研は、各研究会の業界の課題解決、企業の技術力向上、人材育成などの自主的な活動を支援するとともに、産技研が保有する研究成果の技術移転を推進しています。また、研究会相互の交流を促進することで、新たなものづくりの価値創造に向けた取組を支援しています。
(写真:SPE日本支部主催、京都合成樹脂研究会協賛による島津製作所の講演・見学会)
会員相互の交流を促進し、異業種間の連携を通じてイノベーションを創出
研究会の設立の背景
研究会の設立は、第二次世界大戦の終結直後にさかのぼります。まず、繊維産業の生産拡大、ひいては日本経済再建を期して1947年に京都染色研究会が設立され、その後、1950年代にかけて伝統から先進に至る産業分野の研究会が次々と設立されました。
こうした背景には、戦後の日本が産業構造を大きく変革し、高度経済成長期を迎える中で、新技術や素材に対する業界の関心が高まったことにあり、そのことに呼応した産技研も当時の業界の要望をくみ取り、体温を感じながら協調していく体制づくりに取り組んだことが、研究会の設立につながったとされています。
研究会の設立にはそれぞれ独自の背景があり、業界の要望や提言に基づいて設立された研究会もあれば、若手や中堅技術者による自主的な勉強会から発展したものも存在します。
京都の地域企業自らが積極的に新たな技術の向上、人材育成に努めてきた研究会の歴史は、研究会はもとより産技研の歴史でもあります。
会員相互の技術研鑽と交流の場
研究会は、それぞれ独自の特色を持った活動を展開しておられますが、全ての研究会に共通するのは、会員相互の技術研鑽と交流を通じて新たな価値を創造することです。
業界の課題に関連する重要な技術についての理解を深めるための「研究例会」や「講演会・講習会」、企業訪問や関連施設の視察を行う「見学会」の開催、さらには会報誌の発行などを通じて、会員にとって有益な技術情報を提供しています。また、産技研の研究成果を業界に技術移転する場としても機能しています。
研究会の事業は、会員(一部の研究会は産技研が事務局を受託)が協力して運営されており、若手会員を中心に構成されたチームや委員会を設置するなど、研究会ごとに様々な工夫を凝らしながら持続可能な発展に向けた運営に努められています。

2024年11月に開催した産技研UC「創造フォーラム2024」でのユーザーセッション(技術展示ブース)の場を契機に、京都合成樹脂研究会と鍍秀会の間で新たな交流活動が生まれました。

2025年2月に開催された京都染色研究会、京染・精練染色研究会、西陣織物研究会の3研究会合同による研究例会(産技研UC協賛)では、情報工学分野の専門家を講師に迎え、AIの最新動向と進化するAIと人の共存について学びました。
業種の垣根を越えた交流と連携強化による新たなものづくりの創造
産技研では、研究会活動による交流の場を拡大するため、かねてより、京都ものづくり協力会(産技研UCの前身の組織)のもとで、複数の研究会による横断的な活動を支援し、研究会相互の交流や異業種連携を促進してきました。
今後も、産技研UCを通じてあらゆる機関との強固な連携を推進し、伝統技術や先進技術の知恵をいかした新たなものづくりの価値創造に向け、研究会の活動を一層支援してまいります。
研究会にご関心のある方は、各研究会の事務局までお問い合わせください。また、新たな研究分野、技術、産業などのテーマについて仲間と研究してみたい方は、産技研までご提案ください。
研究会一覧
2025年1月末現在 (五十音順)
- #異業種間の連携
- #研究会
- #交流
- #企業の技術力向上
- #業界の課題解決
- #人材育成
- #ユーザーズコミュニティ
- #イノベーション