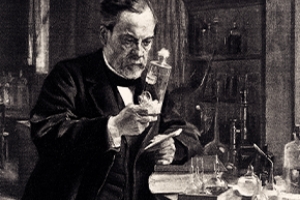京都市産技研 前史(明治~戦後)

~京都・伏見の日本酒醸造技術向上を目指した先人の歩み~
日本の首都といえば東京だというのが現在では世間一般の常識だが、実をいえば、明確に「東京を日本の首都とする」と定めた法律は、21世紀の現在に至るまで存在しない。「岩波日本史辞典」によれば、明治2年(1869)に江戸城が皇居とされ太政官が東京に移されたことと、明治4年(1871)に府県の順序で東京が第一とされたことで、東京が首都の地位を得たとされているが、法的な根拠はないのだ。今でも時折聞かれる京都人の冗談として、「天皇さんはちょっと東京にお出ましになっているだけで、そのうち京都にお帰りにならはります」というものがある。
しかし京都にとっては甚だ残念な史実が残る。明治元年(1868)9月、明治天皇の東京行幸が行われた。天皇は、いったんは京都に帰ってきたが、明治2年(1869)3月、2回目の東京行幸が行われたのち現在まで、天皇が住居として京都に戻ることを選んだことは一度もない。京都から見れば、なし崩し的に江戸城が天皇家の住処である皇居と定められたことになる。
当時の京都人たちは、京都が首都として永遠に繁栄するものと信じていた。天皇が東京に行ったまま帰ってこないということで、この行幸が事実上の「東京遷都」になることを危惧し、動揺した。住民の動揺を目の当たりにした京都府は、「翌年には天皇は京都に戻ってくる」ことを住民に約束し、動揺の鎮静化を試みた。一方で、政府に対しては、京都経済の立て直しのための資金援助を要請し、その結果、明治2年(1869)に、勧業資金として政府から京都府へ15万両が貸与された。
さらに、明治3年(1870)、還幸の延期が伝えられた。つまり、天皇は無期限で京都に帰ってこないことになった。京都人たちは再び動揺する。府は、住民の不安が極度に高まっていることを政府に訴えた。これを受けて政府は、洛中の地子免除を布達し、3月には、「府下人民産業基立金」として5万両を支払う措置をとった。この後、産業積立金は10月に5万両が追加され、合計10万両ほどになった。現在の価値で言うと50億円ほどである。
この資金は、府に対してではなく、天皇という存在を地元から失って動揺する京都の市民に対して与えられたものだった。
京都府は、遷都後の衰退を挽回するため、産業政策を重視した政策を推進した。中でも、工業に重点を置いたが、近代的な工場を新設し、新しい技術を導入、研究するには、多額の費用と設備が必要だった。このため、京都府は、国から交付されたこの産業基立金を元手として、府営の勧業施設を次々と建てていく。
明治初年に京都で開催された京都博覧会は、京都市に再び活気を呼び戻すきっかけとなったが、明治13年(1880)ごろから、こうした府営の勧業施設は次々に民間に払い下げられる。上京区・下京区の区長たちは、この産業基立金を府営の勧業施設の維持に使うのではなく、現金で上下両区に下げ渡してほしいと府に願い出た。明治14年(1881)、産業基立金は上京下京の共有財産として返還された。明治22年(1889)4月1日、上京区および下京区が合体し、京都市が成立する。京都市は、返還された産業基立金を元手とした京都の地場産業振興を行い、そのための施策として様々な博覧会・展示会事業を開催した。
酒造業界に目を向けよう。明治時代の日本においては、酒造業は基幹産業であった。明治7年(1874)の「府県物産表」によれば、酒は生産額ベースで全工業生産高のなんと16.7%も占める工業製品だった。明治政府が、酒税を地租と並ぶ極めて重要な税収源とみなしたのも理解できる。明治10年(1877)には最後の国内内戦である西南戦争が勃発し、それに伴って酒の需要も増えた。酒屋の新規開業は明治13年(1880)にピークを迎える。明治末期には、酒税が国庫収入の首位を占めていた。明治政府は、酒造業を厚く保護した。
江戸時代まで、日本酒は、酒蔵ごとに存在する蔵付き酵母から酵母菌を取り入れて作っていた。しかし、酒蔵には雑菌もたくさん存在したため、日本酒が腐敗してダメになる、いわゆる「腐造」が多発していた。米代や人件費を投下して、一年に一度しか行わない日本酒が腐造になってしまえば、酒蔵が倒産の危機に直面するばかりではなく、国にとっては税収にも響く大問題だった。こういったことから、酒蔵の技術指導と酒造検査は大蔵省が取りしきり、業界の要望によって明治37年(1904)には東京の滝野川に大蔵省醸造試験所が設立された。こうした、国が主導する酒造業育成策は、国の財政に寄与する一方で、酒造業界の近代化にも大いに貢献した。一方、京都・伏見においては、明治42年(1909)11月、大倉恒吉氏が酒造会社としては初の研究所となる大倉酒造研究所を設立、東京帝国大学卒の濱崎秀を初代技師として採用した。ほぼ同時に、伏見酒造組合にも研究所が発足。ひとつの地域に複数の技師が集うのは全国でも異例のことだった。この研究所は大正2年(1913)に休止となったが、これに代わる研究指導機関として、同年伏見醸友会が設立され、月1回の集会を開き、実践的課題の解決にあたるとともに、杜氏講習会、講演会、他産地の見学会などをおこなった。こうした地道な努力が功を奏し、伏見酒の品質は向上を続け、全国にその高品質を知られることとなった。
大正3年(1914)に勃発した第一次世界大戦による好景気を受けて、京都では、陶磁器・染織といった伝統産業以外に、各種の化学産業が興り始めた。それを試験・指導する機関が必要になったことから、大正9年(1920)、京都市工業研究所が業務を開始、大正12年(1923)7月、東九条山王町に新しい工業研究所が竣工した。昭和11年(1936)、工業研究所醗酵部が酒造業界の巡回指導を開始したという記録が残っている。

昭和12年(1937)7月の盧溝橋事件の勃発により、日本は日中戦争に突入していく。同年、酒の生産と販売価格は統制の対象となった。ここから、太平洋戦争、戦後の混乱期と、日本酒業界は苦難の時代を迎えることとなる。昭和18年(1943)、戦局が厳しさを増す中で、酒蔵の数は半分に減らされ、生産能力を従来の50%に、余力は全て軍需産業に回された。この当時、「金魚酒」という言葉が流行った。割水をして販売された日本酒の濃度があまりにも薄いので、金魚を入れてもスイスイと泳ぎ回り死ななかった、という話から生まれた俗語である。市民にとっては、日本酒どころか、生活必需品のほとんどを配給に頼らざるを得ない状況に追い込まれていった受難の時代だった。
そうした苦難を経験し、戦後の混乱期を経て、復興を遂げた日本は高度成長期に入っていく。京都市工業研究所も、社会の歩みと共に成長していった。
(文・山口吾往子)
<参考文献>
アダム・ロジャーズ(2016)『酒の科学』白揚社
吉田 元(1989)「日本における低温殺菌法の発展」,『科学史研究II』28,p25-30
岩田健太郎(2018)「ワインラバーな感染症屋が考える『アルコール発酵』の偉人 微生物学が関係する理由」(https://dot.asahi.com/wa/2018102900056.html?page=2)(最終閲覧:2022-11-5)
大石航樹「人類は遺伝的に『酒飲み』になる運命だった? 1億年前に隠された生物進化の秘密」(https://nazology.net/archives/80281)(最終閲覧:2022-11-5)
公益財団法人 日本醸造協会ホームページ(https://www.jozo.or.jp)(最終閲覧2022-11-5)
国税庁(2021)「日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り」調査報告書「日本酒の歴史」p15-54
その他の歴史を読む
- #酒造りと酵母の歴史
- #京都酵母