
職人紹介 亀井 剛 氏

織りの技術を通して、何千年も前の人の暮らしを身近に感じられる
子どもの時から不思議と心惹かれた「羅(ら)」。羅は、透け感があり夏用の和装に使われる織物ですが、簡単な装置でこんなきれいなものが織れることに、興味を持ちましたね。
今は、綜絖屋として帯地のほかに、多様な織物組織で織られた時代裂(じだいぎれ)などの文化財復元にも力を入れています。
文化財の復元の仕事はおもしろいですよ。はるか昔の織物を見て、「ようこんなん作らはったなぁ」と感心するものがあります。技術を通して心に響いてくるものがあってね。遠い時代が身近に感じられる。私も、何百年か後の人に、同じように思ってもらえる仕事をしたいものです。
見たことのない組織に出会うたびに、考えに考えて、糸の重なりをひもといていきます。復元不可能と言われていた、中国の馬王堆(まおうたい)で発掘された2000年前の衣装は、糸が今使われているものより細くて非常に難しかったです。色々やってきたので、どんな織物でも織れる綜絖をつくる自信はつきましたね。
綜絖屋は、根気のいる単純作業の繰り返しで、若い人が続けるには難しい仕事です。織物は分業で成り立っており、産技研の西陣織コース(伝統産業技術後継者育成研修)では、機装置などの科目を20年ほど教えています。今後は担い手が途絶える工程が出てくるでしょう。そこは残った者が補っていかないといけません。一所懸命やっていたらええもんができるし、悲観はしていませんけどね。
技術解説
織りを操る重要な装置 綜絖(そうこう)とは‥
織物を織る(製織)にあたり、重要な役割を持つ「綜絖」。京都西陣織において、この「綜絖」という言葉は、単体の部品と工程の名称の二通りの意味合いで使われます。
西陣織製作には多くの工程があり分業化されています。「綜絖」は、織物を織る「機(はた)」を準備する工程の中の一つです。
経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の交差により作り出される織物は、緯糸を通すために、経糸を上下に分けて開かせる必要があります。「綜絖」はその経糸を取り付ける部品であり、その集合体である装置は、織る動作の指令役「ジャカード装置」と実際に織る「機」の間に取り付けられ、指令の伝達機能を持ちます。複雑な織物組織※や織密度(おりみつど)で織りあげるためには、経糸の正確な上下運動が重要で、織物の構造や経糸の太さなどを分析し綜絖を設計する能力と、高密度に綜絖を取り付ける緻密な技術が必要とされます。考案された織物が実現できるかどうかは綜絖工程に左右されるといっても過言ではありません。
※織物の経糸と緯糸が規則性を持って交差するパターンのこと。

PROFILE
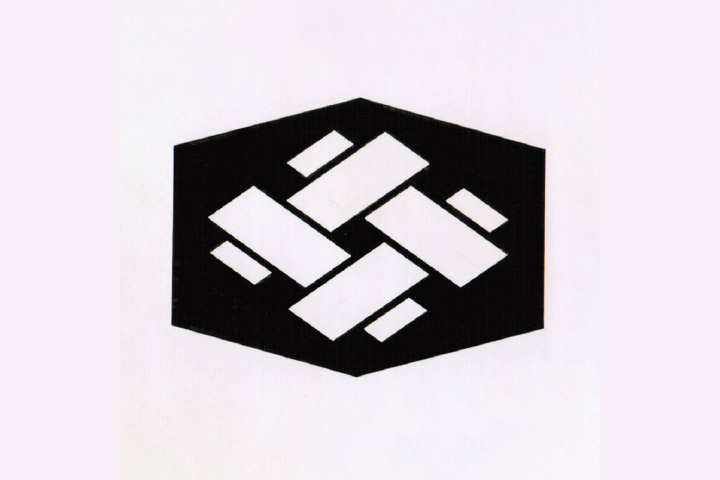
亀井綜絖株式会社
京都市北区紫野北舟岡町3
当ページの本文及び画像の転載・転用を禁止します。
- #綜絖
- #職人紹介
- #西陣織